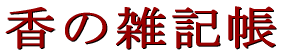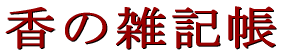|
日本国語大辞典によると、二十四節気とは「陰暦で、太陽の黄道上の位置によって定めた季節区分。初期の陰暦では一年を二十四等分した平気(へいき)であったが、後に黄道を二十四等分した定気(ていき)を採用した。立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨・立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑・立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降・立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒。」とあります。
併せて、五節供(人日・上巳・端午・七夕・重陽)と雑節の一部(土用・節分・彼岸・八十八夜・入梅・半夏生・二百十日・二百二十日)を記しています。(*^_^*) |
 |